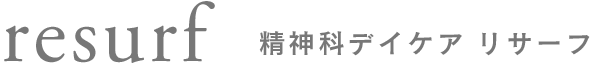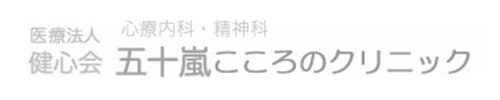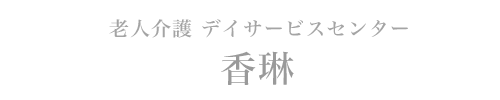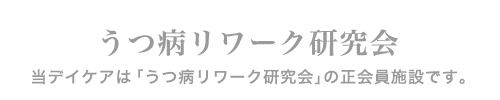「熊が語る,山が聞く」 —マタギの知恵から,自然との向き合い方を考える—
最近,熊の出没のニュースが増えています。
山に近い地域では,怖さや不安を感じる方も多いと思いますが,市街地でも安心できない状況にもなってきています。
わたしは普段登山をしますので,熊のことはずっと気がかりでした。今のような状況になるのはどうしてなのか,何が起きているのか——そんな疑問から,熊について調べてみようと思い,熊といえばマタギについて知るところからだろうと, 今年の春くらいから「マタギ」に関する本を何冊か読みすすめており,ドキュメンタリー映画もいくつか観てみました。
調べていく中で,昔から山と共に生きてきた人たちは,熊をただの「危険な動物」とは見ていないこと,「マタギ」と呼ばれる人たちは,熊の声を聞き,山の気配に常に耳をすませて暮らしていたのだということを知りました。
山に入る前には帽子を脱ぎ,一礼して「おじゃまします」と声をかける。
足跡の向きや風のにおい,木々のざわめきから,熊の動きや山の状態を読み取る。
獲物を見つけても,必要以上には追わず,山の都合を優先する。
命をいただくときは,静かに,迷いなく,過不足なく向き合う。
マタギは命をいただくとき,
「コレヨリノチノヨニイキテヨイオトヲキケ」(これよりのちの世に生きて,よい音を聞け)
と唱えていたそうです。
それは,命を奪うのではなく,命を受け取るということなのだと思いました。
祈りではなく,信仰でもなく,自然との距離を保ち,自然とともに生活していくための知恵なのだと感じました。
「踏み込みすぎない」「奪いすぎない」「語り継ぐ」—そんなふるまいの中に,自然との関係が息づいていたのでしょう。 これは,人と人との関係にも通じるものである気もします。
熊の食糧不足には「どんぐりの不作」が関係していることは周知のことと思いますが,植林された森では実がならない木が多く,熊の主な食べものであるブナやナラの実が十分に育たないことがあるそうです。この,ミズナラやブナの実の豊凶が熊の出没件数に強く影響しています。現在日本の森林の約4割は人工林(植林)となり,残りの約6割が天然林(自然林)とされています。今年はそれらの実が大凶作とのことです。
人工林の多くは戦後の拡大造林によって広葉樹の森を伐採し,スギやヒノキなどの針葉樹を植えた結果うまれたものです。
その結果,熊が人里に出てくることもある——そう考えると,熊の出没は「人間の暮らしに踏み込んできた」のではなく,餌の不作や過疎化による人里の食物(柿・栗・残飯など)の放置が,熊を誘引していると分析されています。
さらに,近年ではシカの個体数も増加しており,下草の食害や植生の変化が進んでいます。これもまた,山のバランスが崩れつつあることの一端かもしれません。
みなさんは,白神山地をご存じですか?
青森県と秋田県にまたがる広大な山地帯です。そこには,東アジア最大級の原生的なブナの自然林が広がっています。
1993年に世界自然遺産に登録されました。
この地域は,多様な動植物が生息する豊かな生態系が保たれていることが特徴です。
現在,白神山地の国指定鳥獣保護区では,原則として動物の捕獲(狩猟・有害駆除など)は禁止されています。特に世界遺産地域の核心部では,厳格な保護措置が取られています。「人の手を加えず,自然の推移に委ねる」ことを基本理念としています。そのため,動物との関わり方も極めて慎重に設計されており,マタギ文化との共存も地域外縁での活動に限られる傾向があります。
マタギの本を何冊か読むなかで,特に印象的だった部分を引用したいと思います。
白神山地が世界遺産に登録される前,このあたりの山に入っていたマタギの証言です。
今から30年程前にマタギの話を聞き集めておられたライターが白神山地で偶然であったマタギとの実際の会話となります。
*以下の引用に関しましては,山と溪谷社さんより,どうぞ掲載くださいと,直接了解を得ております。
また,引用部分の会話は,読みやすさを考慮し,話者を「マタギ」「ライター」として補っています。
マタギ 「たとえば、近道をするために苔の生えている道を通るとか、キノコを根こそぎ採るとかだね。苔を壊せば最低でも五十年生えなくなるから、苔は傷つけないように歩け といわれました。キノコも根こそぎ採れば来年採れなくなる。欲張らず、少しずつ採って来年も再来年も採れるようにしろといわれました。そうやってたいせつにしてきたから千年も続いてきたんだといわれるわけです」
ライター「たいせつにするといっても、白神山地は広いから、歩いて回れるのはほんの一部でしょう」
男は苦笑し、こういった。
マタギ 「歩いていますよ、白神の隅々まで。歩いて把握しておかないと迷ってしまいます。だから、猟以外のときでも歩いています。沢の一本一本、木の一本一本。木が年老い、 寿命がきて倒れます。その下に子どもが芽を出していると、子どもができてよかったなあ、と声をかけたりします。世代交代です。マタギというのは、ただ獲物を獲るだけでなく、山の隅々までを知ってたいせつにしている人のことをいうのです。もし、好き勝手に獲物だけを獲っていたら、今頃、白神には生きものが一匹もいなくなっていたと思います。だからマタギは、ただのハンターと違い、白神の番人だと思っています。」
中略
マタギ 「昔はよかった。今では無駄な道路ができたりしてろくなことはない。白神がズタズタにされました。さらに数年経ったら、世界遺産にでも指定され、いろいろと制約が出てきてマタギができなくなる日が来るかもしれません」
まさかと思った。大昔からここに住み、マタギをやってきた人はどうなるのだろう。
男はマタギ小屋も撤去されるだろうといった。
ライター 「いくらなんでもそこまでしないでしょう。千年、いや縄文の昔から続いてきた日本の文化ですから」
マタギ 「いや、やりかねない。国は、自然を守るというのは、誰も入れないことと思っている。そうなると、荒廃するだけでなく、動物が増えてたいへんなことになります。山のことを知っているマタギが調整してやらないとだめになります。それを知らないのですよ、机の上で考えているから見当違いなことばかりやっている。我々地元のマタギに話を聞こうともしない。白神が荒廃しないで今もあるのは、昔からマタギが守ってきたからなんです。それをわかっていない、というか、わかろうとしない」と男は諦めたようにいった。
今回,マタギの語りに耳をすませることで,自分も,自然との向き合い方を考えていくべきだと思いました。
では,私たちはどうすればよいのでしょうか。
熊の出没は,ただの「自然災害」や「危険な動物の問題」として片づけることもできます。
けれども,背景にある環境の変化や人と自然との距離の変化を見つめることで,私たち自身の暮らしや感覚を問い直すきっかけにもなるのではないでしょうか。
秋田県では,熊による人的被害が相次ぎ,自衛隊が後方支援に派遣されるほどの事態となっています。
このような状況では,山に入ること自体が危険を伴う地域もあり,
まずは地域の情報を確認し,無理な行動は避けることが大切です。
それでも,自然との向き合い方を考えることは,今だからこそ必要なのではないかと思います。たとえば,山に入る機会があるときには,少し立ち止まり,風や木々の音に耳をすませてみること。森の気配を観察することからなら,はじめられそうです。そうして自然と向き合う時間は,単に自然を観察するだけでなく,もしかすると,自分の感覚を少しずつ呼び覚ましていくような時間にもなるのではないかと思います。
そして,マタギが代々,自然との共生の中で大切にしてきたことを語り継いでいくこと。
熊のことも,山のことも,ただ怖がるだけでなく,事実を知っていくこと。それは,自然と向き合うための準備でもあり,自分自身を整える時間でもあるのかもしれません。
怖さの奥にあるものを知り,考え,語り継いでいくこと——それが,今の私たちにできることのひとつだと思います。
それは,自然との関係を見直すだけでなく,
人との関係や,自分自身との関係を見つめ直すきっかけにもなるのかもしれません。
マタギから学ぶことが多すぎて,勢い余ってパワーポイントにまとめてしまいました。周囲からは,いったい誰にむけて,どんな立場として,それをどこで披露するのか,と数々の指摘をうけていますが,「いち人間として,人間にむけて」としか言いようがなく,そのような返事をしております。もしご興味がありましたらお声がけください。この話題をきっかけに,みなさんと自然との向き合い方についてお話できたら幸いです。
K.M.

10 月の木曽駒ケ岳でみつけたシラタマノキ
引用文献:
工藤隆雄(2020)『マタギ奇談』ヤマケイ文庫,山と溪谷社.
参考文献:
工藤隆雄(2020)『マタギに学ぶ登山技術-山のプロが教える古くて新しい知恵』ヤマケイ文庫,山と溪谷社.
滝田誠一郎(2021)『奥会津最後のマタギ: 自然との共生を目指す山の番人』小学館.
中永士師明(2025)『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』新興医学出版社.
林野庁(2024)『令和6年度 森林及び林業の動向』林野庁ウェブサイト.